サピックス特別インタビュー
算数入試で問う力、
数学力を伸ばす授業〜攻玉社中編〜
2025.10.16
攻玉社中学校・高等学校は、算数1科で受験できる「特別選抜」を約30年前から導入するなど、早くから理系人材の育成に力を入れてきた男子の進学校です。その授業の特色と入試の狙いについて、数学科の中野秀太郎先生に伺いました。

広野 中学数学の内容は、大まかに幾何と代数に分けられますが、貴校はどちらに力を入れていらっしゃいますか。
中野 本校における双方のウェイトはほぼ同等です。中1では代数が3単位、幾何が2単位、中2では代数が3単位、幾何が3単位となり、この2年間で中学内容を修了します。
広野 貴校では、中3と高1に「選抜学級」を1クラス設置されています。一般学級と選抜学級とでは、授業内容が異なるのでしょうか。
中野 授業内容はほとんど同じです。ただ、選抜学級のほうが一般学級に比べて進度が速いので、応用問題や入試問題に取り組む時間が多くなるというイメージです。
広野 日ごろの学習において、予習と復習では、どちらを重視していますか。


中野 復習です。なぜなら、予習を前提に学習を進めると、自己流の誤った解き方を覚える恐れがあるからです。たとえば、中1で習う方程式は、一般的に式変形を縦に書いていくという決まりがありますが、それをきちんと教わる前に解くと、計算式をずらずらと横に書き連ねてしまうことがあります。このように、誤った解法が一度身についてしまうと、そこから抜け出すのに時間がかかってしまいますから、できるだけまっさらな状態で授業に臨み、そして授業で未知のことを学ぶ感動を味わってほしいと考えています。
広野 文系・理系に分かれるのはいつからですか。
中野 希望する進路に合わせて、高2から文Ⅰ・Ⅱ、理Ⅰ・Ⅱの四つのコースに分かれます。このうち文Ⅰと理Ⅰは多様な入試に対応するコース、文Ⅱと理Ⅱは国公立大学入試に対応するコースです。1週間における数学の授業数は、文Ⅰが3単位、文Ⅱが4単位、理Ⅰ・Ⅱが7単位となります。
広野 数学を苦手とする生徒に対するサポートや、反対に数学を得意とする生徒に向けた発展的なプログラムがあれば教えてください。
中野 定期テストの成績不振者には、中1から高1まで指名制の補習を行っています。出席しなければ部活にも参加できないため、生徒たちはまじめに受講しています。一方、発展的なプログラムとしては、中1から参加できる希望制の特別講習(特講)があります。数学の特講では、骨のあるハイレベルな問題に取り組むため、小学生のころに算数が得意だった生徒からは非常に好評です。
広野 さて、貴校では、帰国生入試を皮切りに、第1回入試、第2回入試、特別選抜入試とさまざまな機会を設けていらっしゃいます。これらの入試問題を作成するにあたって、意識されていることを教えてください。
中野 すべての入試回に共通している視点は、「与えられた問題をあらゆる角度から試行錯誤し、粘り強く解く力があるかどうか」です。小手先のテクニックだけで問題を解く受験生ではなく、その場でしっかり考えることができる受験生に来てほしいと思っています。
広野 1994年度から算数1教科型入試(特別選抜入試)を続けていらっしゃいますが、2026年度入試からその内容を変更されるそうですね。
中野 はい。これまで特別選抜の入試科目は、算数Ⅰ(50点・50分)と算数Ⅱ(100点・60分)でしたが、新たに、算数[共通](100点・50分)と算数[発展](150点・60分)のA方式、算数[共通]と国語(100点・60分)のB方式からの選択制となります。算数[共通]は、A方式・B方式ともに同一問題で、配点と出題形式は従来の算数Ⅰを一部変更したものになります。一方、A方式の算数[発展]は、配点に変更がありますが、これまでの算数Ⅱと同じ形式・同じレベルを予定しています。
広野 最後に、受験生にはどんな力を身につけてほしいとお考えですか。
中野 定理や定義をしっかり理解し、それらをうまく組み合わせて問題を解決する力を大切にしてほしいと思っています。「感覚だけで解ける」というのは非常に危険なこと。因果関係や論理的プロセスを意識しながら学習を進めてほしいですね。
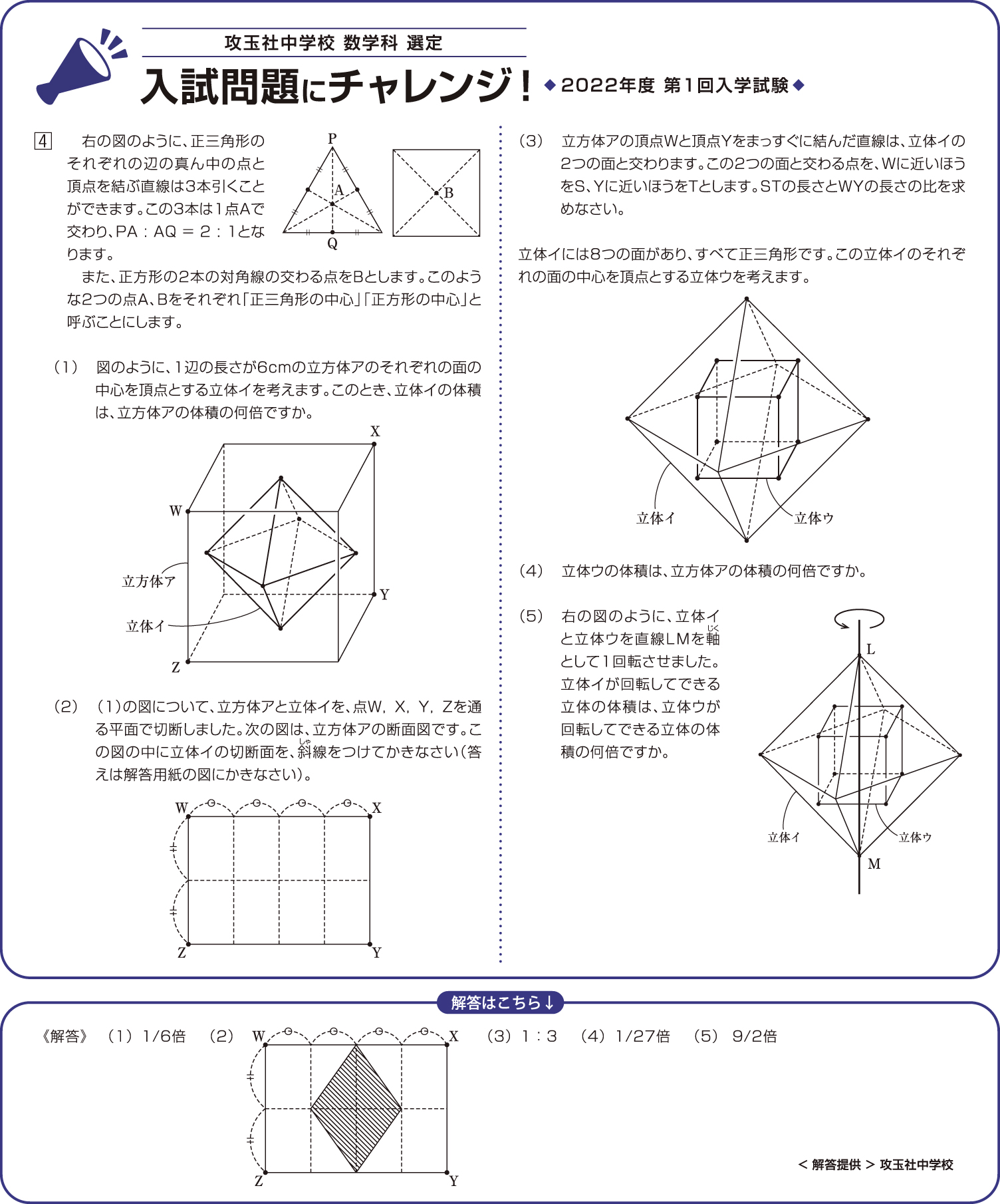
School
Data
- 所在地
- 〒141-0031 品川区西五反田5-14-2
- TEL
- 03-3493-0331
- 学校長
- 藤田 陽一
- 創立
- 1863年創立の蘭学塾を前身に1872年に攻玉社を開校。1947年、攻玉社中学校となり、その翌年高等学校を設立した。
- URL
- kogyokusha.ed.jp

きめ細かいサポートで、6年間一貫教育を推進
1863年に蘭学者、近藤真琴によって創立された私塾を前身とする、歴史ある学校です。校名は詩経の「他山の石、以て玉を攻くべし」(粗悪な石でも玉を磨くための砥石とすることができる)に由来。そこには、知徳を磨くことで、大きな志を持って世界に飛躍してほしいという同校の理念が込められています。そのため、中高6年間を3つのステージに分けて、きめ細かい学習指導を行い、同時に道徳教育にも力を入れながら、6年間一貫教育を推進します。帰国生に配慮した国際学級があるのも特色の1つです。