サピックスの「社会」
社会全体のことを考えられる人間に。「自分たちの問題だと思うことが知識を活かす」とサピックスは考えています。
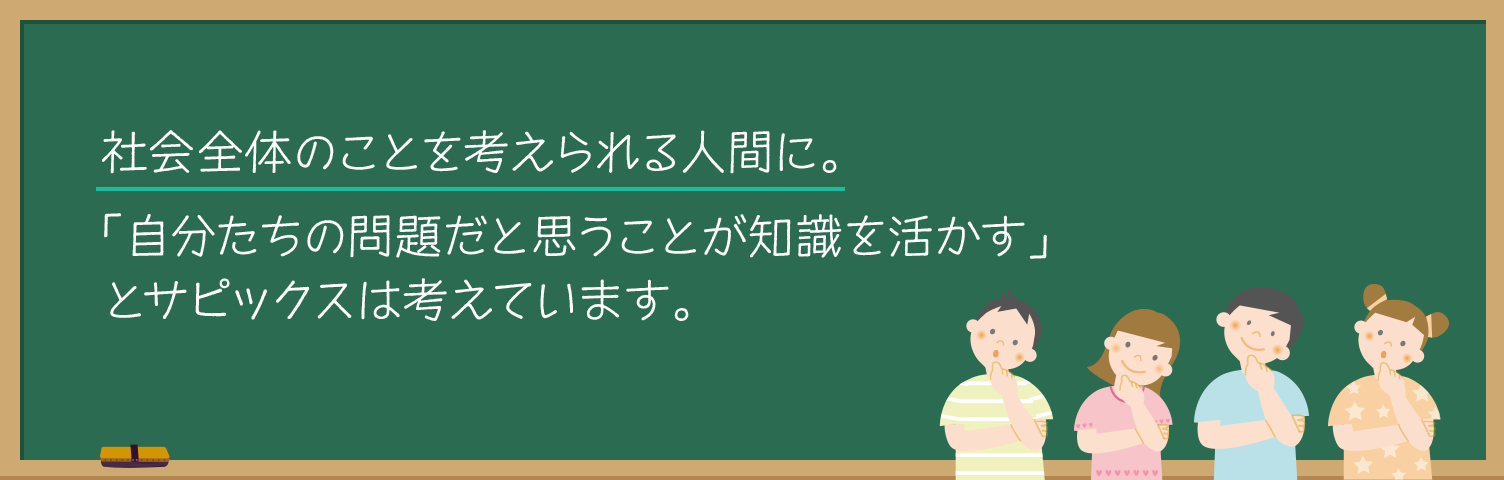
世の中を広く見る力を育てる。
社会科の中に含まれる地理・歴史・公民という三つの分野は、それぞれが幅広く深みのある学習分野です。知識として、あるいは常識として覚えなければならないことももちろんありますが、さまざまなことがらを系統的にあるいは横断的に関連づけることも重要な学習となります。身近なことから世界で起きていることまで、自分自身の問題としてとらえ考えていくことが、断片的な知識に関連性を持たせ、私たちの生きている社会を広く総合的に見る眼を養っていくのです。
 4年生の社会は、地理分野の学習が中心です。この時期の学習内容は、6年生になってからの入試対策のカギを握っているため、正確に身につけることがポイントです。日本の国土の様子から始まり、地方ごとの学習に進んでいきますが、その時に大切になってくるのが地図感覚です。そのためにも、まず都道府県の名前や位置・形、そして川・平野・半島などの重要地名を頭に入れていかなければなりません。その知識がさらに細かい地名、各地の気候や産業の学習の基礎となり、さらに知識の幅を広げていくことにつながるのです。また、実際に入試問題でも出題頻度の極めて高い地図の読解や行政区分、重要地名、気候や産業の特色などをできるだけわかりやすく、また楽しく学習していくことによって、しっかりと消化していきます。地図帳は地理の基本です。いかに多く地図帳を開いたかで、地理が得意になるか不得意になるかが決まると言ってもよいでしょう。したがって、授業でも家庭でも、習った地名を地図帳で確認したり、色ペンで印をつけたりする作業を大切にするよう指導していきます。
4年生の社会は、地理分野の学習が中心です。この時期の学習内容は、6年生になってからの入試対策のカギを握っているため、正確に身につけることがポイントです。日本の国土の様子から始まり、地方ごとの学習に進んでいきますが、その時に大切になってくるのが地図感覚です。そのためにも、まず都道府県の名前や位置・形、そして川・平野・半島などの重要地名を頭に入れていかなければなりません。その知識がさらに細かい地名、各地の気候や産業の学習の基礎となり、さらに知識の幅を広げていくことにつながるのです。また、実際に入試問題でも出題頻度の極めて高い地図の読解や行政区分、重要地名、気候や産業の特色などをできるだけわかりやすく、また楽しく学習していくことによって、しっかりと消化していきます。地図帳は地理の基本です。いかに多く地図帳を開いたかで、地理が得意になるか不得意になるかが決まると言ってもよいでしょう。したがって、授業でも家庭でも、習った地名を地図帳で確認したり、色ペンで印をつけたりする作業を大切にするよう指導していきます。
 入試問題の3本柱の一つである地理分野を夏期講習終了時までに完全に習得することと、もう一つの柱である歴史分野の学習を9月から始めるという点で、極めて大事な時期です。3年生からすでに地理の学習を始めていますが、地方ごとに重要地名、気候、産業、都道府県ごとの特色などをしっかりとまとめ、地理分野の総仕上げをする時期です。5年生では特に、各地域の地形や気候などの特色と産業とのつながりについて理解を深めていきます。地図帳を開いて確認しながら、知識を確実なものにしていくとともに、さまざまな用語・地名などについては、受験を意識して漢字で書けるようにすることが大切です。また、夏休み以降に始まる歴史分野の学習は、5年終了時までに入試の出題範囲を一通り履修します。事件や人物名などそれまで知らなかった語句が数多く出てきますが、因果関係を一つひとつていねいにたどりながらマスターしていきます。時代が進めば覚えることも増えてきますが、この時期に十分学習しておけば、6年生の受験勉強にも余裕が出てくるでしょう。
入試問題の3本柱の一つである地理分野を夏期講習終了時までに完全に習得することと、もう一つの柱である歴史分野の学習を9月から始めるという点で、極めて大事な時期です。3年生からすでに地理の学習を始めていますが、地方ごとに重要地名、気候、産業、都道府県ごとの特色などをしっかりとまとめ、地理分野の総仕上げをする時期です。5年生では特に、各地域の地形や気候などの特色と産業とのつながりについて理解を深めていきます。地図帳を開いて確認しながら、知識を確実なものにしていくとともに、さまざまな用語・地名などについては、受験を意識して漢字で書けるようにすることが大切です。また、夏休み以降に始まる歴史分野の学習は、5年終了時までに入試の出題範囲を一通り履修します。事件や人物名などそれまで知らなかった語句が数多く出てきますが、因果関係を一つひとつていねいにたどりながらマスターしていきます。時代が進めば覚えることも増えてきますが、この時期に十分学習しておけば、6年生の受験勉強にも余裕が出てくるでしょう。
 夏休み前までに入試に必要な学習分野をすべて履修し、その後は入試本番に向けて実戦演習を繰り返していきます。地理分野では日本の産業の特色や問題点、歴史分野では政治・外交・文化の流れを確認しながら、重要年代・事件・人名を整理し、公民分野では憲法の内容や国際社会などを夏休みが終わるまでに一通り学習します。そして最近よく出題される広範囲な時事的要素を含む公民分野の学習など、難関中学の新傾向の入試問題にも十分対応できるように配慮しています。近年の入試では図やグラフ・統計などを読み取り、分析することが求められたり、複数の分野にまたがるようなテーマが問われたりする問題が数多く出題されます。そのため、今まで縦割りで学習してきたことを横断的に理解するような学習も、サピックスでは重要な学習として、教材やカリキュラムに取り入れています。特に難関中学が出題するような問題は、既存の参考書や問題集では扱いにくいものも多くなっています。サピックスでは常に講師があらゆる事象にアンテナを張り、最新のデータや話題を授業に取り入れることで子どもたちの理解を深める工夫をしています。
夏休み前までに入試に必要な学習分野をすべて履修し、その後は入試本番に向けて実戦演習を繰り返していきます。地理分野では日本の産業の特色や問題点、歴史分野では政治・外交・文化の流れを確認しながら、重要年代・事件・人名を整理し、公民分野では憲法の内容や国際社会などを夏休みが終わるまでに一通り学習します。そして最近よく出題される広範囲な時事的要素を含む公民分野の学習など、難関中学の新傾向の入試問題にも十分対応できるように配慮しています。近年の入試では図やグラフ・統計などを読み取り、分析することが求められたり、複数の分野にまたがるようなテーマが問われたりする問題が数多く出題されます。そのため、今まで縦割りで学習してきたことを横断的に理解するような学習も、サピックスでは重要な学習として、教材やカリキュラムに取り入れています。特に難関中学が出題するような問題は、既存の参考書や問題集では扱いにくいものも多くなっています。サピックスでは常に講師があらゆる事象にアンテナを張り、最新のデータや話題を授業に取り入れることで子どもたちの理解を深める工夫をしています。
3年生の社会 (指導方針・使用教材)
「日本」について学びながら、「社会科」的なものの見方を育てる。